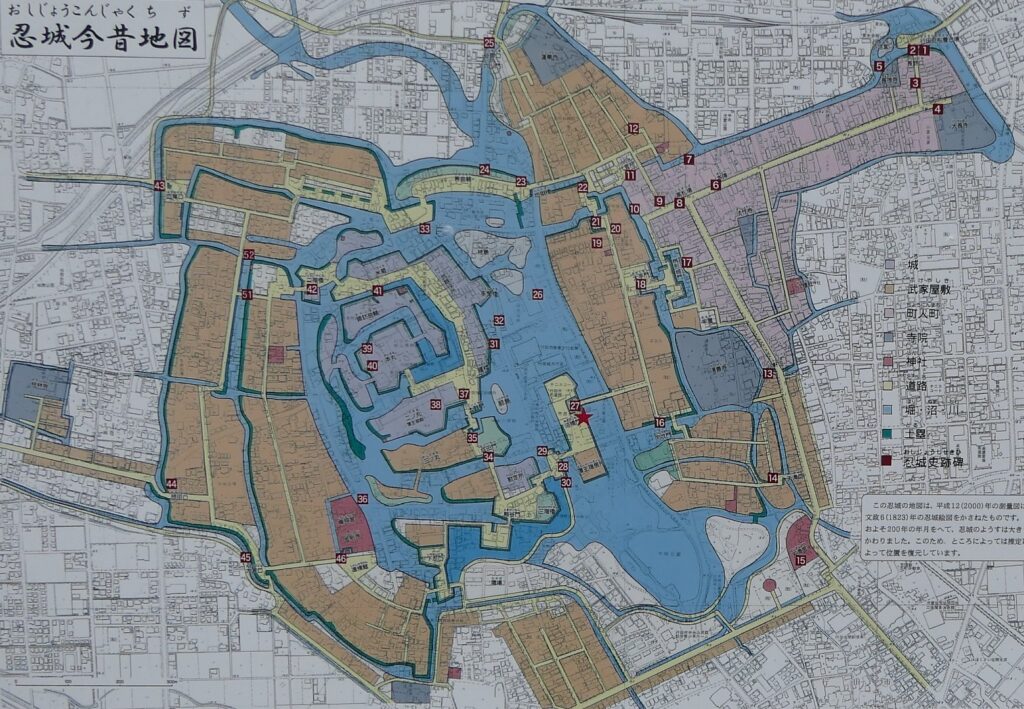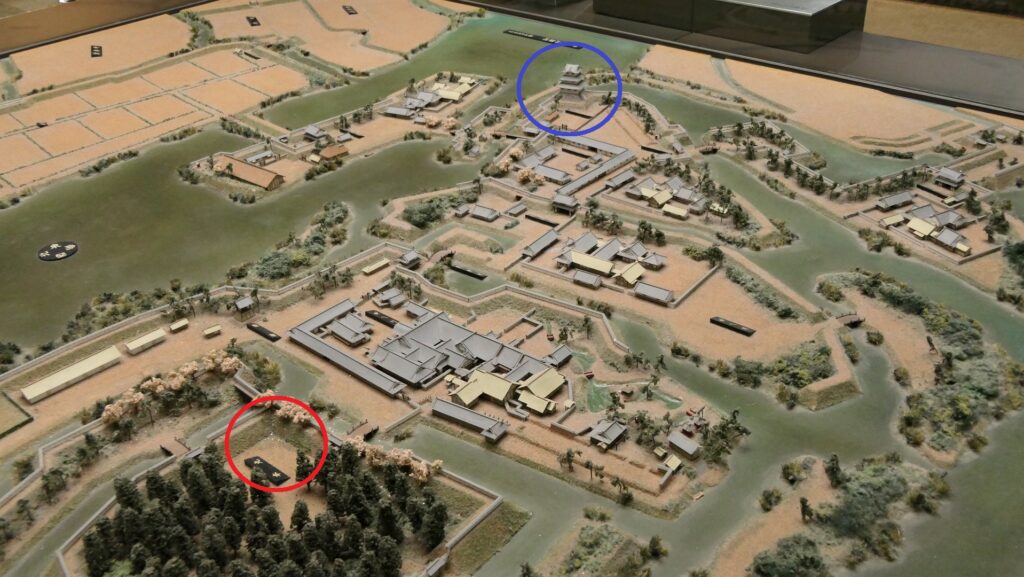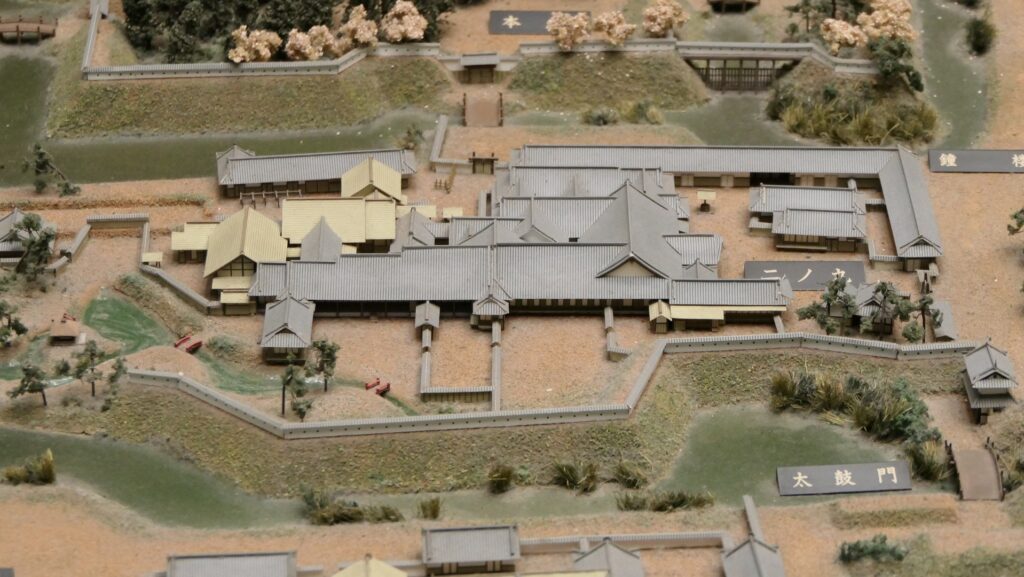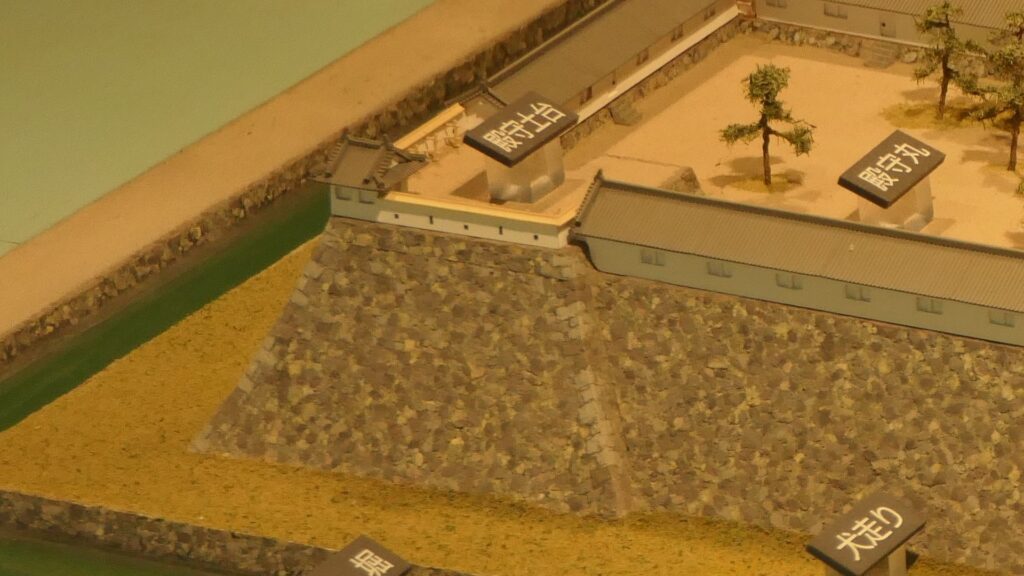特徴、見どころ
城の顔、大手門
現在、飫肥城跡と旧城下町に多くの観光客が訪れています。シラス台地の性質から、城の曲輪群は自然と各々独立したような構成になっています。その多くは今は、神社、学校、グラウンド、住宅地になっています。かつての城の中心部分が、曲輪として現存していて、一般に公開されています。
城周辺の航空写真


ビジターは通常、最初は大手道を、オリジナルの石垣の上にある復元された大手門の方に向かって歩いていきます。そしてここが、飫肥城跡のイメージとして一番よく使われる場所となっています。実は、オリジナルの大手門の詳細はわかっていないのですが、現在の門は飫肥杉を部材として伝統的工法により復元されました。よって、この門もまるでオリジナルであるかのように周りと調和しています。門の内側は、立派な石垣に囲まれた四角い防御のための空間になっていて、桝形と呼ばれます。この門の役割がよくわかります。




土塁と空堀に守られた三の丸
この大手門は、とても大きい三の丸の入口になっています。三の丸は、門の箇所以外は土塁と空堀に囲まれています。門から三の丸の中に入っていくと、内側から4mの高さがある土塁が見えます。ここは城の中でも古い部分に当たります。現地の説明板によると、土塁はかつては外側にある空堀の底から約16mもの高さがあったそうです。



石垣に囲まれている本丸
土塁の反対側には、高く長い石垣とその上の土塀がそびえており、本丸を囲んでいます。本丸の中に行くには、長く広い石段を歩いていき、ここにも桝形があります。その周辺には飫肥杉が生育していて、とても神秘的に見えます。まとめると飫肥城は、長い時を経て、古い時代の土塁と新しい時代の石垣が合わさって築かれていることがわかります。



本丸には、飫肥城歴史資料館があり、城の歴史を学ぶことができます。また、飫肥小学校もありますが、関係者以外の立ち入りはできません。松尾の丸は、本丸のとなりの少し高い位置にありますが、ここには御殿が再建されています。この通りの建物がここにあったわけではありませんが、他所の現存屋敷を参考にして建てられました。珍しい蒸し風呂もあります。

飫肥杉が素晴らしい旧本丸
旧本丸は、城では一番高地にあります。ここに行くにも長い坂を歩いていきますが、ここにも素晴らしい石垣や桝形があります。この曲輪は江戸時代初めに地震により一旦破壊されてしまいますが、飫肥藩は堅固に再建したようです。しかしそれ以来、城主の御殿は新しい本丸に移っていったので、その中には建物がありません。



その代わりに、飫肥杉が一面に植えられていて、苔のカーペットのような地面からまっすぐ伸びています。まさに壮観です。仮にこれらの飫肥杉が、曲輪が再建されたときに植えられたとしたら、350年近く経っていることになります。



曲輪の背面の方には、復元された裏門もあり、ここから出て他の観光スポットに向かうこともできます。